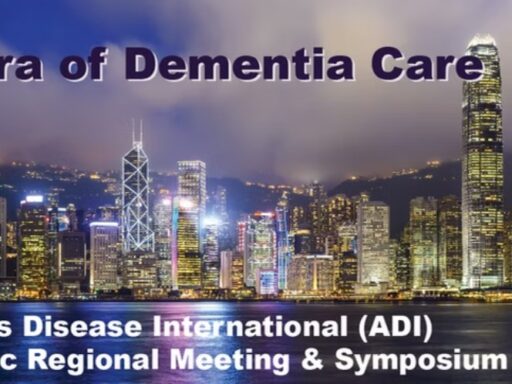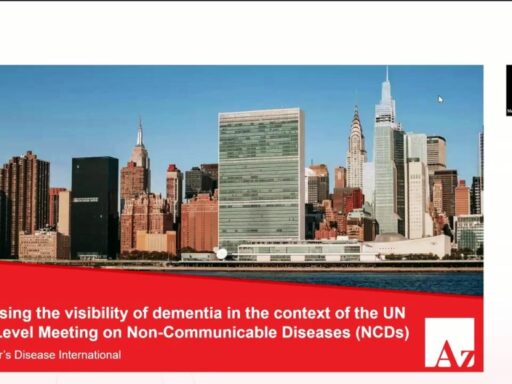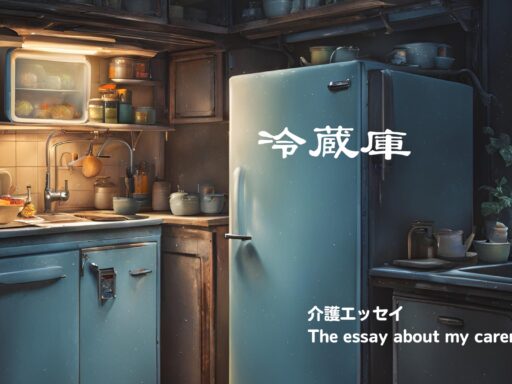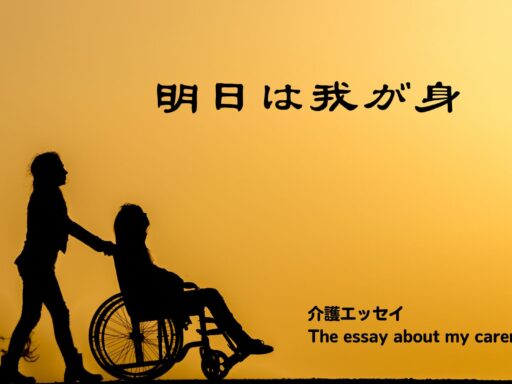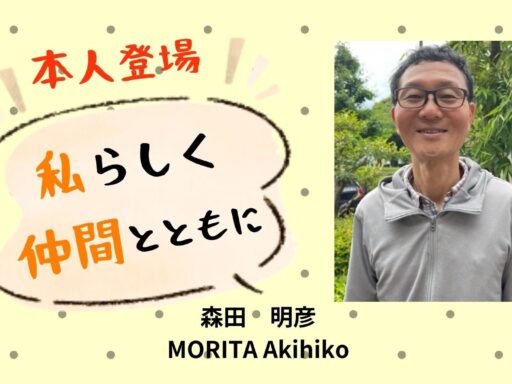オレンジイノベーション・プロジェクト

株式会社日本総合研究所より、国際ネットワーキングイベント「認知症・障がい者等の当事者参画型開発の現在地」に招待され、原等子(認知症の人と家族の会理事、新潟県立看護大学准教授)と馬場美彦(認知症の人と家族の会国際化交流委員)が参加しましたので、ご報告いたします。
日時:2025年10月6日13:00~16:30
場所:東京都大田区羽田空港1-1-4 川崎重工スタジオ Kawaruba
株式会社日本総合研究所は、経済産業省ヘルスケア産業基盤高度化推進事業の一環として、認知症当事者とつくる「オレンジイノベーション・プロジェクト」の事務局を務めています。商品化を行う際に、認知症当事者と一緒に開発することで、より使いやすいものを目指すという取り組みで、すでに多くの企業が参加しています。このような取り組みを「共創」(Co-Creation) というようです。
日本で、視覚障害のある人と共同開発した例として、PLAYWORKS より視覚障がい者歩行テープ「ココテープ」の紹介がありました。視覚障がい者が働くオフィスでトイレまでの導線に貼ってみたところ、トイレに行く際に白杖を使わなくても行けるようになったとのことです。
カナダの取り組みとしては、トロントにある研究機関で、病院や高齢者向け施設などを有する Baycrest が設立した Centre for Aging + Brain Health Innovation における取組みが紹介されました。認知症の関連では、Defy Dementia という啓発ツールが紹介されていました。このツールは、Podcast など複数の媒体で認知症の予防できることを伝えるものです。
デンマークからは、Public Intelligence 社からリビングラボの可能性について紹介されました。リビングラボは、北欧から始まっている取り組みで、当事者の生活する(リビング)場で、社会課題の解決や新しい価値を生み出す取り組みです。デンマークにはそのような施設である Living Lab Vesthimmerlands があります。
本記事を担当している記者の認知症グループホームでも、認知症疾患医療センターの介護ロボット研究事業にお手伝いとして、利用者さんにロボットを使っていただいたこともあります。これも「共創」だったのかもしれません。
イベントの最後には、川崎重工の介護用ロボット「フレンズ」などを紹介していただきました。写真は、「フレンズ」を操作する原理事です。

今回、新しい取り組みとしてズームで音声通訳を行っていました。初めてのことで多少トラブルがありましたが、日本語と英語で質問が飛び交いました。
今後、オレンジイノベーション・プロジェクトからどのような製品が生まれてくるか、期待したいと思います。