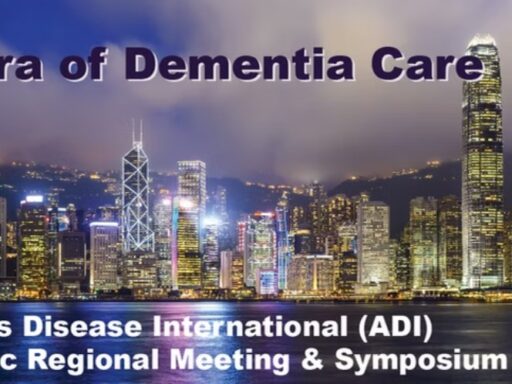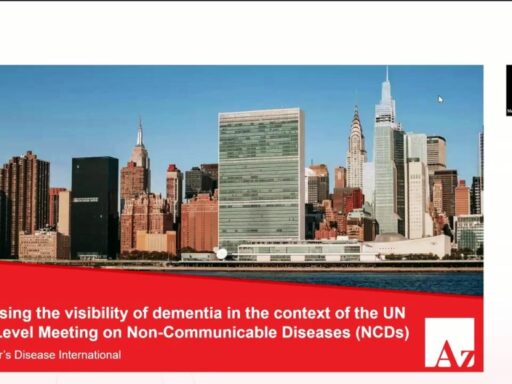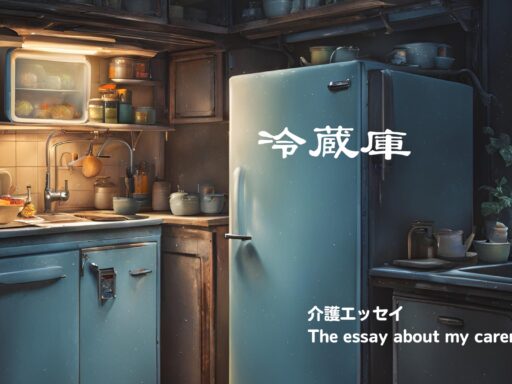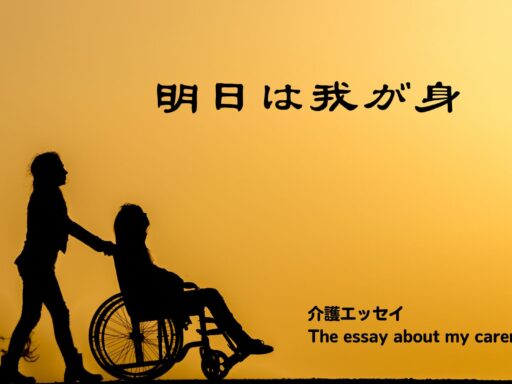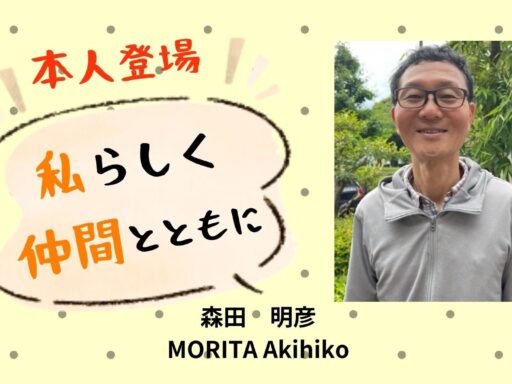【申込受付中】(オンライン開催)HGPIセミナー特別編 認知症月間・世界アルツハイマー月間記念「当事者の経験を語る~認知症研究における本人・家族等の参画~」(2025年9月9日)

今回のHGPIセミナー特別編は、2025年の認知症月間・世界アルツハイマー月間を記念し、「当事者の経験を語る~認知症研究における本人・家族等の参画~」と題し開催いたします。
医学研究全般において、患者・市民参画(PPI: Patient and Public Involvement)は研究を前進させ、社会により必要とされる研究成果を還元するために欠かせない取り組みの一つであり、近年、国際的に重要視されています。
英国では、医学研究の質の向上、社会的妥当性の担保、患者本人や家族等ケアラー等の視点を取り入れた研究の実現を目指す取組みとして、国立医療研究機構(NIHR:National Institute for Health and Care Research)により、研究助成金の申請に際して研究計画へPPIの具体的な方針や実施計画の明記の義務付けなどが進められています。さらに、カナダやオーストラリア、アメリカ等でも、PPIを研究の基盤として位置付ける動きが強まっており、各国の医学研究の中心機関が積極的にPPIを推進しています。
日本も例外ではなく、日本医療研究開発機構(AMED: Japan Agency for Medical Research and Development)が、患者と研究者の協働を目指す第一歩として「AMED患者・市民参画(PPI)ガイドブック」を作成し、より良い研究開発の推進に繋がるPPIの取り組みを推奨しており、特にがん領域や精神疾患領域を中心に取り組みが活発化しています。
このような国内外での潮流を受け、日本の認知症研究領域でもPPI推進への機運が高まりつつあります。2024年に公表された認知症施策推進基本計画の重点目標4に「認知症の人と家族等の意見を反映させている認知症に関する研究事業」に関する指標が盛り込まれました。これにより、認知症研究におけるPPI推進の必要性は政策上にも明確に位置付けられました。他方で、認知症研究におけるPPIの意義や具体的な実装方法に関する認識は十分に浸透しておらず、医学研究および認知症研究におけるPPIの理解の深化が急務です。それゆえに、日本の研究環境においてPPIをより一層推進するためには、諸外国の先行事例における本人の声を日本の認知症の本人や研究者に届け、研究者と実践者双方にとって学びの場を設けることが求められています。
そこで、HGPIセミナー特別編では、オーストラリアで認知症のアドボケーターとしても活動しながら、認知症研究のPPIの第一線で勢力的に活動されている、ボビー・レッドマン氏をお招きし、実際の経験や課題、研究へ参画することの意義について、本人の視点から共有いただきます。また、ディメンシア・オーストラリアでレッドマン氏をはじめとした本人の研究参画の支援に尽力されている研究部門 当事者参画コーディネーターのサラ・ジェイ氏を交えながら、認知症の本人が研究に参画する際に現れる障壁や方策についてお話いただきます。
本セミナーが、日本の認知症研究者や認知症の本人が、認知症研究におけるPPIがどのように創られ、実践され、推進されてきたかについて具体的に理解を深める機会となることを期待しています。また、この場を通じて、日本の認知症研究におけるPPIのさらなる発展に向けた一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
※本セミナーのスペシャルコメンテーターとして、日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事 山中しのぶ氏の登壇が決定いたしました。レッドマン氏とジェイ氏の講演を受け、日本の認知症本人の視点から、今後国内の認知症研究における本人参画への期待についてご発信いただきます。
【開催概要】
- 日時:2025年9月9日(火)17:00-18:30
- 形式:オンライン(Zoomウェビナー)
- 言語:英語/日本語(同時通訳あり)
- 参加費:無料
- 定員:500名
■登壇者プロフィール
ボビー・レッドマン(前頭側頭型認知症の本人/心理学者(退職)/元ディメンシア・オーストラリア諮問委員会 委員長)
ボビー・レッドマン氏は前頭側頭型認知症とともに生きる退職した心理学者。2016年に診断を受けて以来、彼女は認知症の人々とその介護者の生活向上を決意し、情熱的な認知症啓発活動家として活動している。ボビーは最近、オーストラリア全土の認知症とともに生きる人々のために、そして彼らとともに働くディメンシア・オーストラリア諮問委員会の委員長を退任。現在は、公衆衛生と障害に焦点を当てた数多くの委員会に参加している。認知症研究の強力な支援者として、彼女は時に参加者として、時に助言者および/または研究者として50以上の研究プロジェクトに関わり、多くのオーストラリア国内外の会議で発表を行っている。ボビーは強い地域とのつながりを持ち、活発なロータリアンとして、ロータリー地区認知症啓発・支援委員会の委員長を務めている。2020年には、地域および認知症啓発活動での功績により、シニア・オーストラリアン・オブ・ザ・イヤーのニューサウスウェールズ州ファイナリストに選出されるという大きな栄誉を受けた。
サラ・ジェイ(ディメンシア・オーストラリア研究部門 参画コーディネーター)
サラ・ジェイ氏は、ディメンシア・オーストラリアの研究部門 当事者参画コーディネーターを務めている。認知症と共に生きる人々または経験を有する人々が研究プロジェクトに参画できるよう支援し、研究者やプロジェクトと連携して、そうした人々の意味のある研究参画を可能にするための能力構築を行うことを中心に取り組んでいる。以前は研究者として活動し、博士課程およびその後の研究では、交代勤務が睡眠、健康、安全、ウェルビーイングに及ぼす影響の解明を専門とした。
山中 しのぶ(日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事)
1977年生まれ、高知県在住。2019年に41歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断され、2021年に15年間勤務した携帯販売営業職を退職。2022年4月に一般社団法人セカンド・ストーリーを設立。同年10月に香南市で「でいさぁびすはっぴぃ」を開設し、2024年には高知市でも事業を展開。2022年7月に「高知家希望大使」に任命され、2024年4月に世界アルツハイマー病協会のGlobal Dementia Experts Panel国際本人委員に就任。2025年4月にはレビー小体型認知症の診断も受ける。同年6月、日本認知症本人ワーキンググループ代表理事に就任。著書『ひとりじゃないき 認知症と診断された私がデイサービスをつくる理由』(中央法規、2025年)。