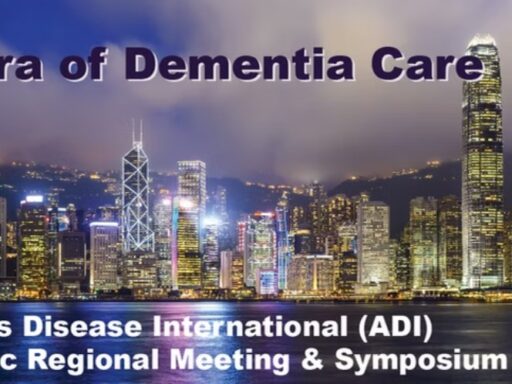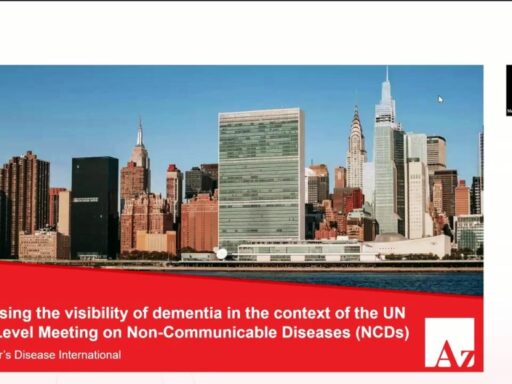介護エッセイ「書き魔」

※お母様の介護のために単身赴任を選択された「家族の会」会員の福井さんが日々の介護生活をエッセイにまとめられ、ご応募くださいましたので、ご紹介します。「日本認知症国際交流プラットフォーム」では、広く原稿を募集しています。皆様からの介護体験もぜひお寄せください。
書道との出会い
父が70歳で亡くなったのが1994年、おかんは66歳だった。そのあと書道を趣味とするようになったようだ。JRで駅三つ離れた町の書道教室に習いに行っていたと聞く。車の免許は持たず、移動手段は原則歩きと公共交通機関のおかんは、雨ニモマケズ、風ニモマケズ、書道教室にせっせと通っていたようだ。今も足腰が年齢に比して丈夫なのはその頃歩いて鍛えていたことが少しは影響しているのかも知れない。元来ひと付き合いが良く、社交的なおかんは書道教室で人脈作りにも精を出したのだろうか。書道からさらに発展して俳句や短歌の仲間との交流もあったらしい。おかんの写真アルバムには、書道教室の先生を囲んだ仲間たちとの食事風景や、書道展会場でのスナップ写真が何枚も挿み込まれている。また、顔ぶれの違うメンバーによる俳句会の小旅行(「吟行」というそうな)で、こちら九州の名所や旧跡での笑顔の集合写真なども見つかる。写真裏面の日付等で察するに、おかんの70代は、人生で も輝いていた時期だったのではないか。そのころあまり交流のなかった息子はアルバムを眺めながら勝手に推測している。
書道、俳句、短歌…おかんの美しき黄金時代
思えば仕事一筋のわがままな夫(つまり私の父)に付き従って大阪から熊本に引っ越し、慣れない土地でおかんは家のことを懸命に切り盛りしていたはずだ。その夫たるや、家のことはそれこそ柱に釘一本打つこともない人で、仕事以外の趣味はゴルフと酒だった。そんな生活が響いたのかどうか、晩年は病を得て入退院の繰り返しだったが、今にして思うに私の父本人の闘病生活よりもおかんの看病生活のほうが大変だったのではないか。そんな生活も、父がこの世と別れを告げたその時から、ある意味解放された。寂しさ悲しさ後始末を乗り越えてひと段落つき、それからがおかんの美しき70代、黄金時代の到来だった。おかんは自由になった時間のほとんどを書道、俳句、短歌につぎ込んだ。それらの作品は、大小さまざま額装を施したり、短冊にしてみたり、写真アルバム風にまとめてみたりと、意匠をこらした形で残されている。また2010年に建てた父の墓石の正面には、おかんの手になる「南無弥陀仏」、墓の正面下には亡父に捧げる内容の俳句まで彫りこんでもらっている。その他にも色紙やらなにやら、おかんの作品はこの住み慣れた古い家のあちらこちらに残されている。なかでも大作の取り組みとして、自作の短歌百首を短冊にしたため、それらを経典のような折り本に作り込んだものがある。一応百首、数はそろえてはある。日常心に触れたこと、孫への思い、季節の情景などを題材に、やわらかな仮名の筆文字で書かれている。しかしそのうちの二割ほどはまだ鉛筆書きだったり、文のテニヲハを決めきれずにおかれていたり、朱で傍線が引かれていたりと未完成のままだ。そして、いまのおかんは、それらの作品に手を加えるようなことは一切せず、ただ陽のあたる縁側で手に取ってずっと眺めて過ごしている。
認知症を疑うきっかけ
思えばおかんの認知症を最初に疑ったきっかけも、そのこだわりの趣味、書道に絡むものだったように思う。10年も前になるだろうか、一枚の写真を見ながら、「この作品、一生懸命書いたんだよ。良く書けていたのに盗まれたんだよ。盗んだやつ知ってるんだよ。ぶっ殺してやりたいよ」とか、その人は盗んだ次の日死んだとか、穏やかならぬことを興奮気味に話す。その写真をのぞき見ると、書道展の会場風景で、おかんの書いた、人の背丈以上もある書道の作品が掛け軸になって展示されている。その前にはおめかししたおかんが「どうだ」とばかり鼻の穴をややふくらませ気味にして立っている。素人の作品を盗むなどにわかに信じがたいので、おかんが勘違いして家のどこかにしまい込んでいるんじゃないか。そう思って家探しを敢行したところ、巻物状態になって保管されていたその作品が見つかった。それをおかんに示したところ、「あっそう」とひとこと、見つかったことをさして喜ぶわけでもなく、こちらとしては拍子抜けでそのときは終わった。そして別の機会におかんが同じ写真を見た時、また同じセリフが興奮気味に始まる。そしてそれは何度も繰り返されるようになった。
「認知症…かな?」
書く、書く、書く、…
おかんはとにかく書く。デイサービスでは自由な時間のほとんどを書写に費やしているそうな。標語集や人生訓を手本にして、施設で用意いただいたチラシやコピーの裏紙をとじたものに、ひたすら筆ペンで、「ありがとうの毎日を」てな文を書き写す。家に戻ってからも書く。日課としては、デイサービスから帰った後、毎回その介護施設に宛てて「今日でデイサービスはしばらく休みます。お世話になりました。」との手紙を書く。お歳暮のツナ缶20個のフタ全部に、いただいた自分の妹の名前と「ま・ぐ・ろ」の文字。家の備品にも書き込まれた名前だらけだ。スリッパの甲の部分に大きく自分の名前か私の名前。来客にはちょっと出しようがないものとなる。タオルにも同様に名前を書くのだが、油断してはならないのは、筆ペン(水性インク)使用のとき。そうとは知らずに濡れた顔をふいてしまい、いきなり仕事あがりの炭坑夫になってしまった。無念。ビン詰めのふたにも中身が何であるかを必ず書く。それはまあいいのだが、中身を食べ終わり使い終わってビンを再利用する際には、フタに「梅干し」と書かれたものの中に佃煮が入ることもある。つまりはフタの表書きを読むだけでは中身が何だか分らない状態になってしまうのだ。それよりなにより一番の出来事は、デイサービスから持ち帰った着替え済みの洗濯物のなかに「作品集」を紛れ込ませていた時だ。知らずに一緒に洗濯機を回してしまい、終ってフタを開けてびっくり。中の衣類が細かなパルプといっしょにこねられてまっ白に。洗濯ものと洗濯機を元に戻すのに3~4時間はかかったろうか…。
おかん一代 まだまだ続く
おかんの口癖「人は一代 書は末代まで。足跡は残らないが、手形はずっと残る。」おかん有事の際は作品全部お焚き上げと考えている親不孝息子としては、正直この口癖を耳にするたび少しひるんでしまう。が、字を書くことは脳を刺激して、認知症対策としても効果的と聞いたことがある。おかん95歳、自分一代の長さの秘訣はそんなところにもあるのかもしれない。
おかんがまだ70代、今は未完のままの百首の短歌集作りに一生懸命だった頃、よく聞かされたものだ。「わたしはこの百首短歌を完成させるまでは絶対死ねないよ…。」
死ねないおかんとの暮しはまだしばらく続く。
執筆:福井