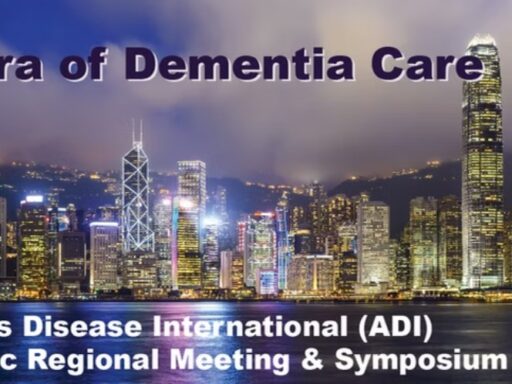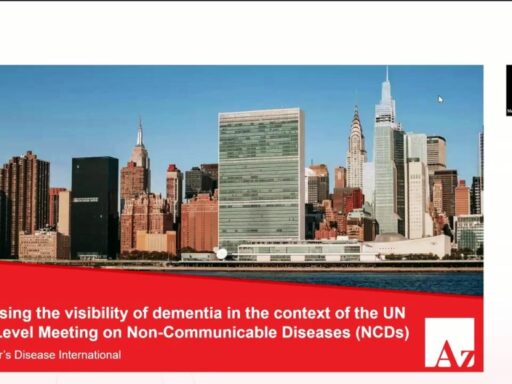介護エッセイ「おふくろの味」

※お母様の介護のために単身赴任を選択された「家族の会」会員の福井さんが日々の介護生活をエッセイにまとめられ、ご応募くださいましたので、ご紹介します。「日本認知症国際交流プラットフォーム」では、広く原稿を募集しています。皆様からの介護体験もぜひお寄せください。
「おふくろの味」
会社勤めを62歳で退職し、熊本でひとり暮らしのおかんを支えるために、札幌の自宅に妻と猫2匹を残しての単身介護生活を始めて4年が過ぎた。そのおかんも今年95歳、食欲もありよくしゃべり、元気そのものだ、アルツハイマー型認知症の進行以外は…。
昔のことは覚えているが、今日したことや言ったことがすぐ頭から消えてしまうおかん。私との会話内容の種類もだんだんと減ってきて、今では数パターンになってしまった。しかも、ついさっきおこなった「言った行為」そのものを忘れるので、聞き手からすると同じ話を何回も我慢しなければならない羽目になる。でもおかんからすればすべてが最初の会話内容なのだ。「そんなのにこにこ笑って適当にあしらっておけばばいいのに」と思う方、それを4年続けられる人間は普通いませんから。もう最近は無視するか「ははは」と笑うか、または「うん」「ああ」と声を出す程度が関の山だ。うちのおかんはそれに加えて自分史の歴史年表もぐっちゃぐちゃになってしまっていて、おかんの日課の「縁側での思い出浸り」でも、死んだ人が生き返ってみたり既婚者が独身になってみたりの変幻自在、歴史の歪曲。
ただ、そんなおかんの状況を私が都合よく利用させてもらっているのもまた事実だ。私はおかんの暮す、築50年の「トミちゃん基地」から自転車で3分のアパート住まいをしているのだが、夕方片付けが終わって基地を出る時には必ず「用事で出かける。明日の昼過ぎに戻る」旨の書き置きを残していく。そして次の朝5時には基地に戻って炊事や洗濯など家事を済ませたうえで7時半に仕事に出かけるのだが、おかんが起きてくる前にその書き置きを処分しておきさえすれば、何事もなく「オハヨー」と一日が始まっていくのだ。夕方私が実家を出る時には、パターン会話のやりとり。
おかん:「〇〇行くんか」
私:「うん」
おかん:「明日の昼帰るんか」
私:「うん」
おかん:「じゃ昼ごはん作っとくわ。何がいい?」
…ここから先は応用編。私の返事はときに「親子丼頼む」だったり、ときに「カレー食べたい」だったり、いろいろバリエーションをつけてみる。これはおかんの脳トレになるようで、たいてい数秒の沈黙の後、作れないことの言い訳をする。親子丼の場合、「鶏肉買ってこなかったわ」、カレーだったら「カレー粉切らしたわ」。うん、話の筋は通っている。
でも、その名前の料理自体がどんなものなのか、なかなか思い出せなくなってしまった品目もあるようだ。先日同じパターン会話が始まった時、私が作ってほしい料理を「八宝菜」とひねってみたところ、私の発する音声は聞えているものの、どうもその音とことばの意味が結びつかないようで、
私:「八宝菜」
おかん:「え?はんぺん?」
私:「八宝菜」
おかん:「あんぽんたん?」
このやり取りがしばらく続くのだ。で、ついには思い出した!
おかん:「はっぽうさいか、野菜にアンコかけたらしまいや…」
ちょっとビミョーだけど。
ただ、はからずもこんなアホみたいなやり取りが、今度は私の記憶中枢をするどくピンポイント刺激してしまうときもある。そう、私が思い出してしまった「おふくろの味」。
家族が一緒に大阪市内で暮していた小学4年生のころ、私に余部(あまるべ)博くん(一応仮名)という同級生がいた。新学期からの転校生で、そんなに親しいというわけでもなかったが、普通に遊んだりしていた。少々肥満気味、目の大きい愛嬌ある顔立ちの、よくしゃべる明るい少年だった。彼の家に行ったことも何回かある。うちから歩いて15分くらい、昭和の語彙でいうところの「文化住宅」、つまりは二階建ての長屋。間取りはおぼろげながら、二階に病気療養中のおばあちゃんがいつもベッドで寝ていたのは覚えている。でもなぜおばあちゃんが寝ている二階にわざわざ上がっていたのかは思い出せない。子ども部屋があったからなのだろうか…。そうそう余部くんには二つ下の弟がいた。それも兄とは全然顔立ちの違う、色白のハンサムな少年だった。なぜそんなこと覚えているのか。それは二人があまりにも雰囲気の異なることに、子ども心に相当驚いたからだろう。
当時の周りの友達は、たいてい母親は専業主婦で家にいて、遊びに行ったときはきちんと挨拶せなあかん、お菓子もらったときなんかきちんとお礼「ありがとう」言わなあかんと少しは気を張っていたものだが、余部くんのうちへ遊びに行くときはその緊張はない。家でおかあさんと会うことは一度もなかったから。家でおやつを出してくれるのは余部くんで、それもまた私にとってちょっとした驚きで、逆にうらやましかった覚えがある。
ウチで一緒に遊んだこともある。何をしたんだったか、プラモデルでも作ったのか、ボードゲームでもしたんだろうか。で、夕方遅めになり、うちのおかんが余部くんに、ウチで夕飯を食べていかないかと誘った。余部くんは嬉しそうに「食べる」と応じた。おかんは「余部くんおかあさんに連絡せんでもええんか」と聴いたところ「ええねん言わんでも。うちにおらへんし…」。以前おかんには彼の家の様子を話したことがあった。おかん自身父親を知らず、母親も40歳で他界している。そのせいなのか、家庭環境が気掛かりな私の友達には常に情を寄せる。「今度余部くんウチに遊びにきてもろたら?一緒にごはんたべたらええわ…」
さて待つことしばし、夕食に具されたのが「八宝菜」。味の記憶は曖昧だが、きくらげとウズラの卵が入っているのが、おかんの少年客へのおもてなし感を前面に押し出していた。少なくとも私はそう感じた。その八宝菜はちょっとだけ気取り系の深皿に盛られていた。カレー皿ともいうのか、茶色トーンの、ペイズリーのようでもあり、ツタが規則的に絡まっているようでもある模様が付いていた。うちの食卓にそれらが並べられ、あったかい湯気が上がっていた。そこでのはっきりとした記憶、余部くんの嬉しそうな楽しそうな、ワクワクもしてそうな表情、おしゃべり、幸福な空気。これを「おいしい」と呼ぶのかもしれない…。おかんごちそうさまでした。
余部くんと一緒だったのは数か月、二学期が始まる前には大阪府下、和歌山県に近い町に引っ越していった。その後しばらくして余部くんから、新しい町でも元気でやっているとの手紙をもらった。そこに差出人として書かれた苗字は忘れてしまったが、珍しくもないものに変わっていた。
古い記憶を蘇らせてしまった次の朝5時、いつものようにアパートからトミちゃん基地に戻り、おかんが起きて来ないうちにルーティンの「書き置き処分」をしようと、たいていは台所のテーブル辺りにある紙を探し出した。
その右下隅の空白箇所には、「八宝菜」と鉛筆で残されていた。
(福井)
執筆:福井
翻訳:牧野優子、アメミヤ マサコ